資格試験の勉強を始めたい人に人気なのが社労士と宅建士です。
でも、「難易度や合格率はどっちが高いんだろう」「年収UPや転職に有利な資格ってどっちだろう」と悩んでいる人も少なくありません。
また、ダブル受験やダブルライセンスを狙いたいけど、どっちを先に受験するか迷っている人も多いです。
この記事では、社労士と宅建士の難易度・合格率などを比較し、ダブル受験・ダブルライセンスのやり方やメリットも紹介します。
社労士と宅建士の予備校比較は、社労士の予備校おすすめ比較と宅建士の予備校おすすめ比較にまとめています。
\【2023年8月20日まで】30%OFFセール中/
社労士(社会保険労務士)と宅建士(宅地建物取引士)の難易度
社労士と宅建士の試験について、4つの基準で比較します。
- 合格率:試験の合格率
- 勉強時間:合格に必要な標準的な勉強時間
- 試験内容:試験の科目・時間・出題形式など
- 勉強方法:暗記・条文理解・横断学習の要否など
社労士と宅建士の難易度比較①:合格率
| 比較 | 社労士 | 宅建士 |
|---|---|---|
| 受験者数 | 40,633人 | 226,048名 |
| 合格者数 | 2,134人 | 38,525名 |
| 合格率 | 5.3% | 17.0% |
| 難易度 | △ | ○ |
合格率から見て難易度が高いのは社労士です。2022年度の合格率は社労士が5.3%、宅建士が17.0%で大きな差があります。
社労士試験は毎年1桁台の合格率なのに対し、宅建士は15~18%程度で推移しているのが特徴です。
社労士の合格率の推移
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |
| 2021 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |
| 2020 | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |
| 2019 | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |
| 2018 | 38,427人 | 2,413人 | 6.3% |
| 2017 | 38,685人 | 2,613人 | 6.8% |
| 2016 | 39,972人 | 1,770人 | 4.4% |
| 2015 | 40,712人 | 1,051人 | 2.6% |
2015年には2.6%まで下がっていますが、2017年以降は6%台で推移しています。
合格者数は毎年2000∼2500人前後です。
10人中1人合格できるかどうかという難易度の高い資格であることが分かります。
宅建士の合格率の推移
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 226,048名 | 38,525名 | 17.0% |
| 2021 | 234,714名 | 41,471名 | 17.7% |
| 2020 | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% |
| 2019 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% |
| 2018 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% |
| 2017 | 209,354人 | 32,644人 | 15.6% |
| 2016 | 198,463人 | 30,589人 | 15.4% |
| 2015 | 194,926人 | 30,028人 | 15.4% |
過去5年間だと合格率は15~18%程度で推移しています。
受験者数は20万人前後、合格者数は3万~3万7000人くらいで、社労士試験と比較するとけた違いに多いのが特徴です。
社労士と宅建士の難易度比較②:勉強時間
| 比較 | 社労士 | 宅建士 |
|---|---|---|
| 勉強時間 | 1000時間程度 | 300時間程度 |
| 難易度 | △ | ○ |
独学した場合の標準的な勉強時間は、社労士が1000時間くらい、宅建士が300時間くらいと言われています。
社労士の方が宅建士より3倍以上の時間がかかる計算です。
社労士試験の方が科目が多く、覚える内容も多くなっています。
社労士と宅建士の難易度比較③:試験内容
| 比較 | 社労士 | 宅建士 |
|---|---|---|
| 受験資格 | あり | なし |
| 試験内容 | ・科目:多い ・時間:長い ・形式:複数 | ・科目:少ない ・時間:短い ・形式:択一式のみ |
| 難易度 | △ | ○ |
試験内容は、「受験資格」と「試験内容」に分けて比較します。
受験資格
| 比較 | 社労士 | 宅建士 |
|---|---|---|
| 受験資格 | ・学歴 ・実務経験 ・試験合格 のいずれかを満たす必要あり | なし |
| 難易度 | △ | ○ |
社労士試験を受けるには、大学卒業などの「学歴」、公務員などの「実務経験」、行政書士試験の合格などの「試験合格」という要件を満たす必要があります。
宅建士には受験資格はありません。
誰でも受験できるわけではないという点で、社労士の方が難易度が高いと言えます。
試験内容
| 比較 | 社労士 | 宅建士 |
|---|---|---|
| 試験内容 | ・科目:10科目 ・時間:午前80分、午後120分 ・形式:択一式、選択式 ・問題数:78問 | ・科目:4科目 ・時間:120分 ・形式:択一式 ・問題数:50問 |
| 難易度 | △ | ○ |
社労士と宅建士の試験科目を一覧形式にまとめました。
| 比較 | 社労士 | 宅建士 |
|---|---|---|
| 試験科目 | ・労働基準法 ・労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法 ・雇用保険法 ・労働保険撤収法 ・労務管理その他労働に関する一般常識 ・社会保険に関する一般常識 ・健康保険法 ・国民年金法 ・厚生年金保険法 | ・宅地業法 ・権利関係 ・法令上の制限 ・税金その他 |
| 難易度 | △ | ○ |
社労士試験は、10科目(択一式8科目、選択式7科目、重複科目あり)合計78問を、午前80分・午後120分で回答します。
宅建士試験は、4科目の択一式50問を120分で回答することになります。
科目数、問題数、試験時間ともに社労士試験の方が多いです。
社労士と宅建士の難易度比較④:勉強方法
| 比較 | 社労士 | 宅建士 |
|---|---|---|
| 難易度 | △ | ○ |
社労士試験の勉強方法
社労士試験は、科目が多いうえに択一式と選択式という2つの形式があるので、各形式に慣れる必要があります。
前提となるのは基礎知識の暗記です。
予備校の講義を聴いたりテキストを読んだりして合格に必要な情報を抑え、インプットとアウトプットを繰り返して記憶を定着させます。
過去問を解いて頻出のカテゴリーや問題をピックアップし、内容を覚えることも大切です。
また、重要な条文や最高裁判例を覚える必要もあります。
社労士試験によく出題される判例の論点とそれに関連する条文を押さえておくことは必須です。
講義やテキスト、過去問に出てくる条文と判例くらいは覚えておきたいところです。
さらに、社労士試験で問われる法律・年金・保険などは密接に関連しているので、個別の理解はもちろん複数カテゴリーをまとめて理解することも大切です。
実際の試験でも複数のカテゴリーにまたがる問題がよく出題されるので、カテゴリーを横断した学習が求められます。
宅建士の勉強方法
宅建士の勉強は、暗記学習がメインになります。
試験に頻出の基礎知識や過去問の内容を覚えておけば、本試験に対応可能です。
講義やテキストに登場する条文や判例については、大まかな内容を理解しておけば回答できる問題が多いので、暗記までは必要ありません。
また、試験科目が少なく各科目の配点も違うので、「重視すべきカテゴリー」が限定されています。
具体的には、配点が多い宅建業法と権利関係を中心に学習することが大切です。
社労士と宅建士の難易度は個人の知識経験でも変わる
「合格率」「勉強時間」「試験内容」「勉強方法」のいずれも、社労士の方が宅建士より難易度は高いです。
ただし、受験する人の知識や経験によって試験の難易度は違ってきます。
例えば、社労士事務所で働いていれば仕事で年金や保険の知識を得ているので、社労士の勉強の方が簡単に感じるはずです。
そのため、自分の知識経験を踏まえて取得しやすそうな資格をまず取得するのも一つの方法です。
また、難易度だけでなく、「仕事のスキルや年収アップにつながるかどうか」という視点で受験する試験を決める人も少なくありません。
社労士と宅建士 年収UPや転職に有利なのはどっち?
結論から言うと、業界によって異なります。
社会保険事務所などの職場であれば、社労士資格があると資格給をもらえることがありますし、転職も社労士資格がある方が有利です。
でも、建築会社や不動産会社、金融機関などでは宅建士資格の方が重宝されます。
社労士資格が年収UPや転職に有利になりやすい勤務先
社労士資格が年収UPや転職に有利に働く勤務先は、次のとおりです。
- 社会保険労務士事務所
- 士業事務所
- 一般企業の人事部
- 一般企業の総務部
- コンサルティング企業
- 予備校
宅建士資格が年収UPや転職に有利になりやすい勤務先
宅建士資格が年収UPや転職に有利に働く勤務先は、次のとおりです。
- 不動産仲介会社
- 不動産管理会社
- 不動産デベロッパー会社
- 金融機関
- 一般企業の財務部
社労士と宅建士のダブル受験・ダブルライセン
社労士と宅建士はダブルライセンスを狙うことができます。
社労士とのダブルライセンスに向いている資格
社労士(社会保険労務士)とは、労働・社会保険に関する法律を専門的に取り扱う国家資格です。
ダブルライセンスに向いている資格は次のとおり。
宅建士とのダブルライセンスに向いている資格
宅建士(宅地建物取引主任者、宅地建物取引士)とは、宅地や建物の売買・交換・貸借の契約に関する説明などを行うことができる国家資格です。
ダブルライセンスに向いている資格は次のとおり。
社労士と宅建士のダブル受験は可能か
試験の日程はかぶっておらず、日程的にダブル受験は可能です。
でも、社労士試験から宅建士試験まで2ヶ月弱しかなく、勉強する内容が大きく異なることを考えると同じ年にダブル受験するのはハードルが高めです。
社労士と宅建士のダブルライセンスのメリット
社労士と宅建では専門分野が大きく異なるので、ダブルライセンスに大きなメリットは見当たりません。
社労士なら行政書士や中小企業診断士、宅建士なら司法書士や不動産鑑定士などの資格でダブルライセンスを狙った方が、仕事の幅を広げやすいでしょう。
ただし、中小企業に勤務する場合は、職域の異なる複数の専門分野で活躍できる人材は重宝されます。
例えば、不動産会社で人事や総務の手続きに精通した人材は高く評価され、収入面も優遇されやすいです。
そのため、ゼネラリストとしての活躍を目指すなら、社労士と宅建士のダブルライセンスを狙う価値はあります。
社労士と宅建士の試験に合格する方法
社労士も宅建士も独学で合格するには300~1000時間程度の勉強が必要です。
十分な学習時間が確保できる人はともかく、働きながら資格を取得しようと思うと相当な期間がかかってしまいます。
年収アップや転職のために短期間で合格したいなら、予備校や通信講座を活用するのが一般的です。
社労士も宅建士も多くの予備校が対策講座を開講していますが、短期間で合格を目指せる講座は限られています。
予備校を比較して、自分の置かれた環境でも無理なく勉強を続けて合格できそうな講座を探しましょう。
例えば、アガルートの社労士講座やアガルートの宅建士講座なら、社会人でも短期間で効率的に学習して合格を目指せます。
特に、同じ年にダブル受験して合格を目指すなら、社労士か宅建士の勉強の少なくとも一方は予備校を利用して効率的に学習を進めないと厳しいです。
ダブル受験向けの講座や割引制度を設けている予備校もあるので、チェックしてみてください。
社労士と宅建士の難易度比較まとめ
社労士と宅建士では、試験の難易度は社労士の方が高くなっています。
ただし、受験する人の知識や経験によって難易度は変わるのは、他の資格試験と同じです。
また、資格取得後の年収アップや転職のしやすさは仕事のジャンルによって異なります。
スキルアップや年収アップ、転職などの目的に応じて取得する資格を選びましょう。

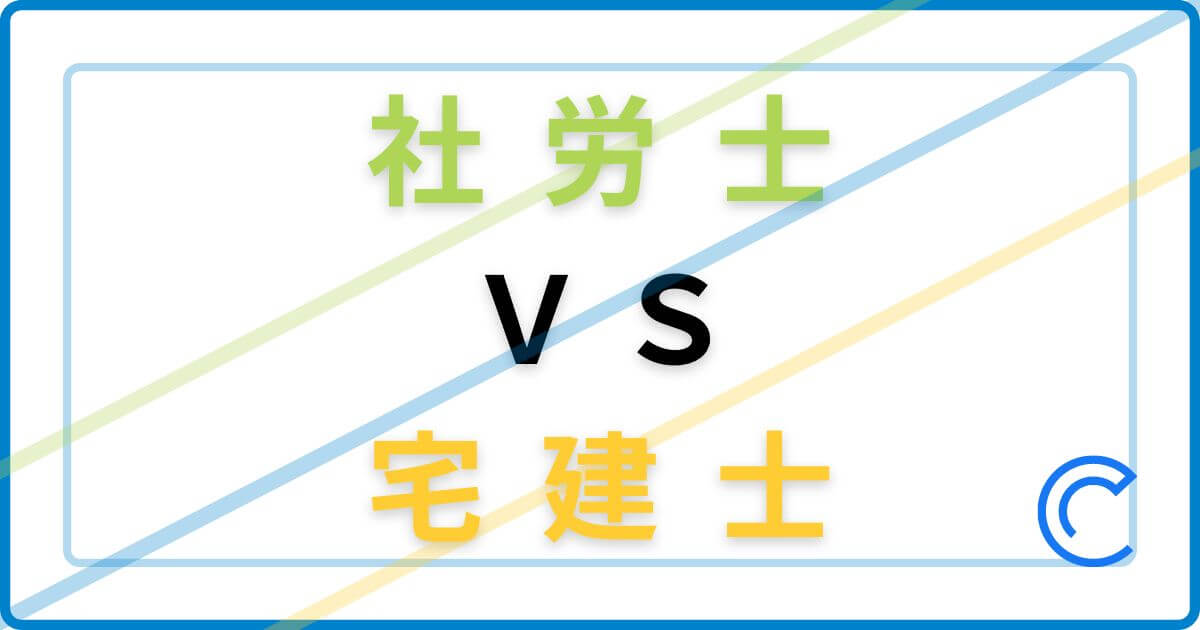


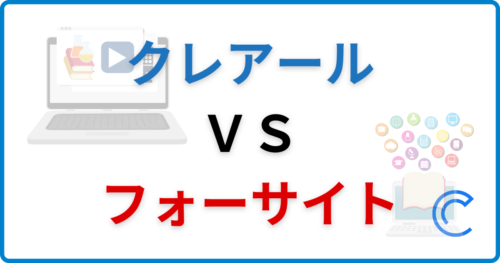
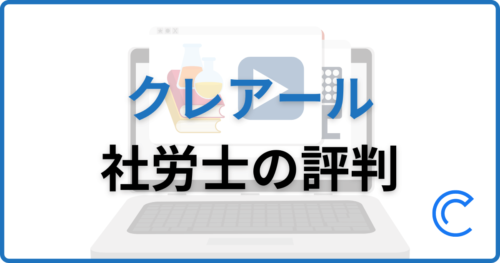



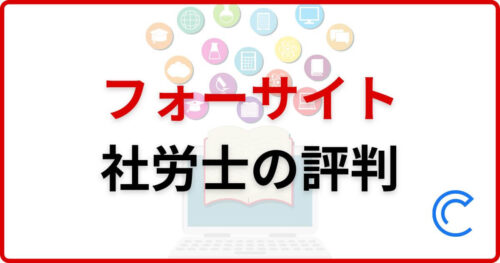
コメント